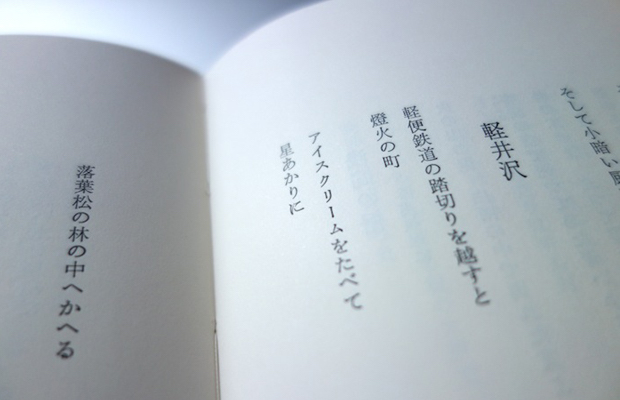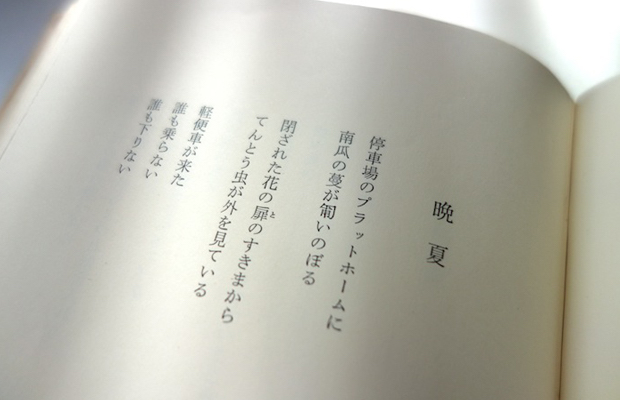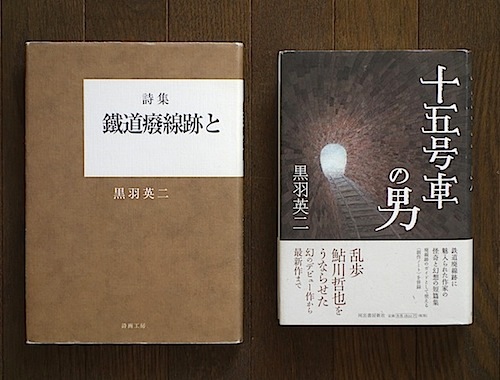軽便鉄道をうたった詩人たち[1]
草軽電鉄を題材とした詩としてよく挙げられる作品に、津村信夫(1909-1944)の「小扇」がある。
「小扇」(『愛する神の歌』1935・四季社)
嘗つてはミルキイ・ウエイと呼ばれし少女に
指呼すれば、国境はひとすぢの白い流れ。
高原を走る夏期電車の窓で、
貴女は小さな扇をひらいた。
「ミルキイ・ウエイ」と命名したある女性との思い出を綴ったもので、「夏期電車」という言葉が、草軽の「あさま」号などのサマーカーを連想させる(詩はサマーカーの登場以前に書かれたようだが)。
ちなみに私は、この詩を「とれいん」No.7(1975.7)掲載の、軽井沢の文学と鉄道を紹介した「風立ちぬ」(ぎんがてつどう著)で知った。
当時の私は中学生、こうした記事を載せた「とれいん」が、とても大人向けの趣味誌に思えたことを憶えている。
ところで、草軽をモチーフとした詩人はほかにもいた。「とれいん」には紹介されなかったものの、津村信夫と同じ「四季」派の田中冬二(1894-1980)も、幾篇かの詩を残している。
「軽井沢」(『橡の黄葉』1943・臼井書房)
軽便鉄道の踏切りを越すと
燈火の町
アイスクリームをたべて
星あかりに
落葉松の林の中へかへる
冬二には「軽井沢の氷菓子」と題した詩もある。軽井沢駅で売られていたそれは、レモン味の青色をしたものだったという。
「軽井沢の冬」(『橡の黄葉』1943・臼井書房)
霙(みぞれ)の中の軽井沢の灯
遠く霙の中の軽井沢の灯
今その灯の下には新刊の書物も
黒パンも珈琲もない
今そこにあるものは古錆びた自転車と
炭酸水の空壜(あきびん)と干大根
草津軽便鉄道の踏切の
ベルも鳴らない
前掲の夏に対し、こちらは冬の情景である。草軽電鉄こと草軽電気鉄道は、1924(大正13)年まで「草津軽便鉄道」と称していた。
2篇とも踏切がでてくるが、「遠雷」という作品にも「踏切のベルが鳴つて 草津行の電車が過ぎた」とある。また、「草軽線たちにしあとのしづけさや」という俳句も詠んでいるが、これなども踏切の光景だろう。いずれも旧軽井沢駅前の通りを横断していた踏切と思われる。
「信仰」(『故園の歌』1940・アオイ書房)
いつしか慣はしとなり風呂の火をみる度に
私はひとり口の中に云ふ
――軽井沢十分停車 草津線のりかへ と
それから風呂の中では
――天狗の湯 天狗の湯 天狗の湯
鹿の湯 鹿の湯 鹿の湯
白骨温泉 白骨温泉 と
〈後略〉
かつては風呂といえば薪風呂だった。その風呂を焚くときに、冬二は軽井沢駅のアナウンスを真似るのが口癖だったようである。
旅行好きだった冬二は、草軽のほかにも鉄道をモチーフとした詩を数多く残している。
「日本海」(『海の見える石段』1930・第一書房)
夜汽車の凍つた硝子に
吐息が描いた猫
ペルシャ産のうつくしい猫
スノー・セットを出ると
窓硝子にアイスクリームのやうな灯(ひ)が映つて
青海(あをみ)といふ駅
しらしらと夜明のうすあかりの中に
日本海は荒れてゐる
ペルシャ産の猫やアイスクリームといった言葉が可愛らしい。
「林檎の花」(『春愁』1947・岩谷書店)
フランネルのやうに暖い
うすあかるい夕暮
林檎の花々の中を
電燈を点(とも)したばかりの温泉行きの電車が走つてゐる
それはフレッシュな外国製の罐詰のレッテルのやうである
ここにある「温泉行きの電車」は湯田中へ行く長野電鉄らしい。夕暮れの中の林檎の花と、灯りのついた電車の光景が、なにかの缶詰のラベルを思わせたのだろう。
変わったところでは馬車鉄道に乗車する随筆がある。1927(昭和2)年に富士を訪れた際のもので、当時は富士周辺に馬車鉄道がいくつか残っていた。文中にある、上井出-富士宮(身延線)間の富士軌道は、1939(昭和14)年まで営業を続けていた。
「三里ヶ原」(『高原と峠をゆく』1955・中央公論社)
人穴から上井出の村へ出た。上井出から大宮―今の富士宮まで、煙草畑の中を鉄道馬車に揺られながら、私は眠つた。
大宮へ着くと、大宮の町は登山客で、まるで祭のやうに賑はつてゐた。
冬二は1894(明治27)年生まれで、少年時代には、東京の本所区(現・墨田区)や日本橋区(現・中央区)に住んでいたこともあり、銀座通りを走っていた馬車鉄道の思い出を綴った随筆もある。
*掲載詩の出典
『津村信夫全集』1(1974・角川書店)
『田中冬二全集』1-3(1984-85・筑摩書房)